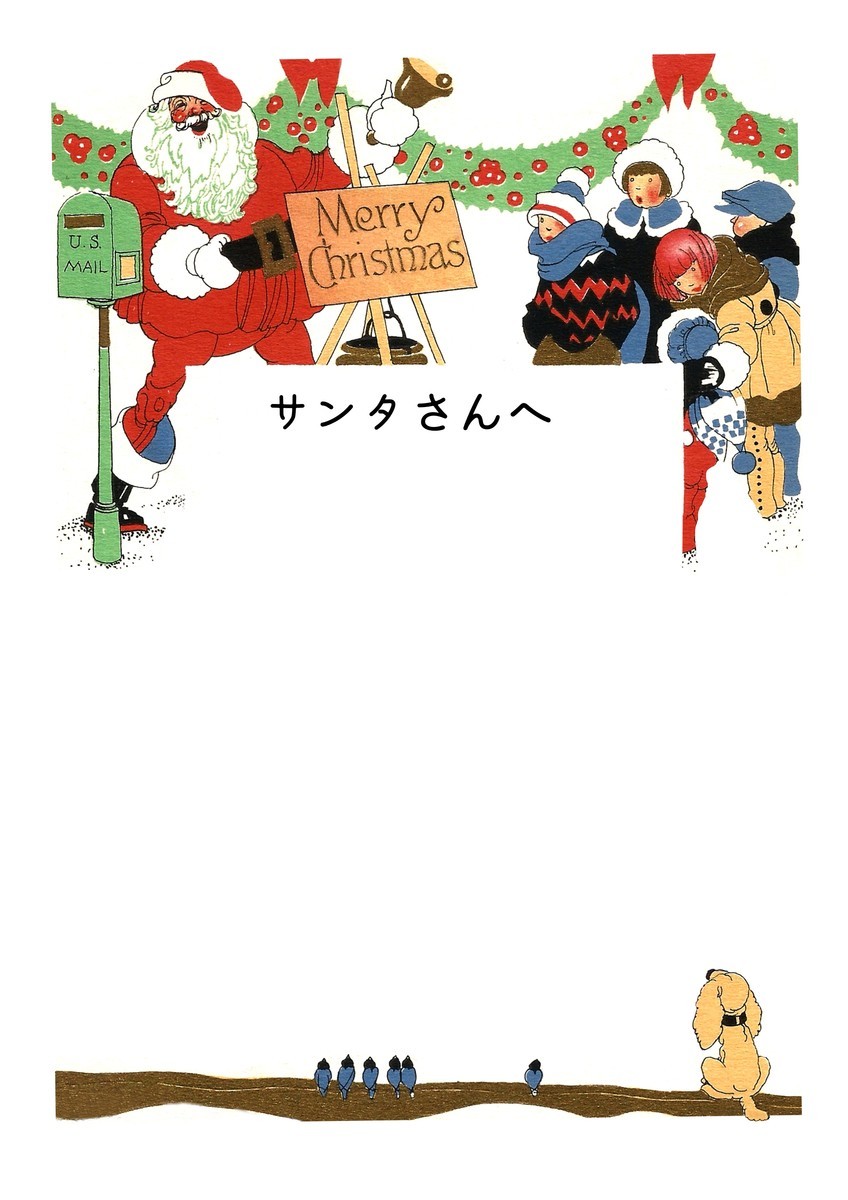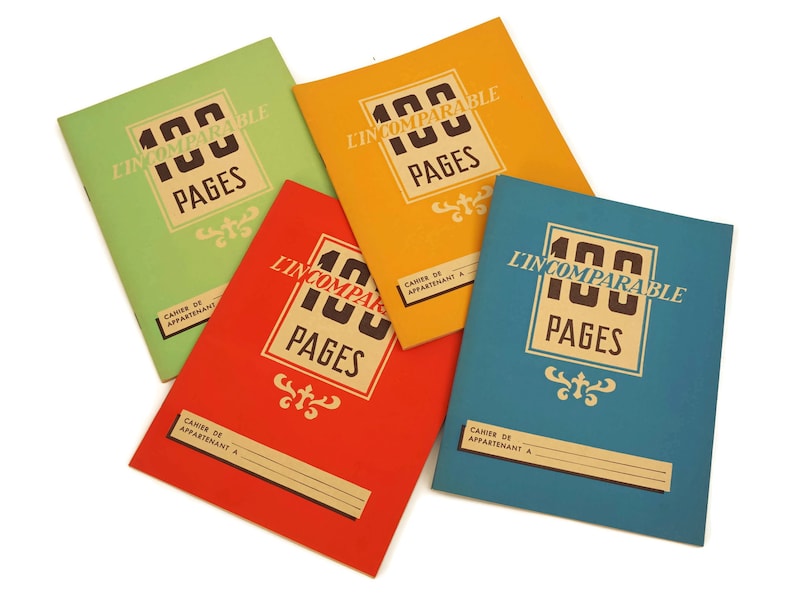helloみなさん、お買い物してますか?
たびたびEtsy大好き!を公言している私ですが(※断じて回し者などではありません)、仲間が見つかりません。Twitterなどで、どうしてみんな買わないの?と聞いてみると、「海外から買うのが怖い」「途中でロスト(行方不明になって届かない)したらどうしよう」「言葉が通じない」といった不安があるとのこと。
みんなが思ってるより、Etsyのお店は「素人集団」ではありません。もともとは手作り品を売る場所だったと思うのですが、最近は、他にお店も持っていて、Etsyにも店舗を持っているというお店が多いです。私はここまでの買い物で、「買ったモノが届かなかった」ことは実は一回もないんですよね(「これ関税で一回開封されて、もう一度閉じられたな」ということは一度あった)。以前はPayPalしか使えませんでしたが、現在はクレジットカード対応しています。
UIが使いづらくて、全然見つけられない・人気商品もわからない、という頃もありましたが、最近では日本語翻訳も部分的に進んでいたり、レコメンドや人気商品紹介機能も進んできて、だいぶ使いやすくなりました。
それでもやっぱり、最初のお買い物はハードルが高いし、送料や、届くまでの時間を考えると、億劫になっちゃう気がします。(海外からの買い物は、決済までの時間にいろいろ考えてしまって、そうこうするうちに衝動が消えてしまうという声もw)
今回は、あらためて私が「なぜEtsyが好きか」という話を書くのに加えて、私が実際に買ったお店を紹介します。私が先に買ってるわけだから、少なくともそのお店は信用できそうでしょ?皆さんも気に入るお店があるといいなと思います。

あらためてEtsyが好きな理由その1 変なものがいっぱいある
この「変」は、いい意味です。あんまり予想ができないデザインや、アイデアに出会えるのが一番楽しいです。
私は昔から洋書の雑誌を見るのが好きで、海外に行ったら買って帰っていたのですが、Etsyは世界中の雑誌のアイテムコーナーを見てる気分になれます。なんとなく、「今この国ではこういうのが流行ってるんだなぁ」とかも分かります。日本の手作り集合サイトもあるのですが、なんとなく「日本の手芸が好きな人の好みの集合体」みたいになってしまっている印象で、良くも悪くも似通ってます。私にとっては「なにこれ?」というものがあんまりない場所なんです。
雑誌フィガロでパリ特派員のお土産コーナーに載ってたようなグッズを、自分で選んで買うことができるのって最高だと思いませんか…?
「パリの子ども部屋」とか読むの好きだった方や、IKEAで本場っぽいクリスマスの飾り買っちゃうような人には、めちゃくちゃ楽しい場所です。例えば日本のアクセサリーショップだと、落ち着いた色合い・小さめの石ばっかりになりがちだったりしますが、Etsyだとカラフルだし、素材も色々で楽しいです。

最近「!?」ってなったのは、70年代アメリカの着せ替え本

メキシコのお店のシューズ
Etsyが好きな理由その2 ビンテージ・アンティークもある
フランスに行ったらクリニャンクールに行きたいし、「東京蚤の市」にも何度も行っている人、私だけじゃないと思うのですが、Etsyはこれらもすごい量で売ってます。アメリカのビンテージショップは古着が強いし、北欧は陶器や刺繍の飾りが強いし、フランスだと銀食器やビンテージドレスが強いです。アンティークやビンテージって、もちろんプレミアがつくブランドなどもありますが、「一個しかなくてめちゃくちゃ可愛い」ものって、他の人にはわからない価値、プライスレスだと思うんですよね。日本のアンティークショップのバイヤーさんだって、そういう一期一会の出会いを大事にして買い付けてると思うし。
ただ、もしこれが東京や赤坂の蚤の市だと、正直2時間歩くとヘロヘロですが、Etsyなら「フランスの古着見たあとインドのビンテージ布見てアメリカのクリスマスオーナメント見る」とか5時間ぐらい余裕でできるとこが、いいとこですね。

最近こういう新品キッズがよく着てますが、これは80年代のUS古着

フランスの1920年代のシャツ
Etsyが好きな理由その3 世界の文化に出会える
所詮は物欲でありただの買い物なので、あんまり高尚なことは考えてないのですが、「やべえマジでかわいい」と思うものって、大抵そのデザインの歴史が古いんですよね。kunelとかお好きだった方はわかると思うのですが、その地でずっと受け継がれてきた物語のあるデザイン・モノって、オリジナリティがすごく強いし、歴史の積み重ねで洗練されていっているし、流行とか蹴散らす美しさがあるなと思います。
「〇〇族」の伝統工芸は、世界のどこの国のものでも超絶おしゃれです。
「なんかこれ可愛いなー、ここに繰り返し書いてあるSamiってなに?」とかってggってみると、スカンジナビア半島に住むサーミ族の伝統工芸でした。とか、そういうことがよくあります。日本でも人気のあるキリムやギャッベなども、もちろんEtsyでも売っているのですが、現地でどういう人たちがそれらを作っているのか、「ユーザー詳細」を見ると分かったりします。織り方とかもね。
私はフェアトレード専門店などでお買い物はあまりしたことがありません。トレードがフェアだろうが、デザインが好みじゃないものは買いたくないからです。そこでいくとEtsyでは、自分の好み先行で選べるから嬉しいですね。その上で、現地の人たちの収入源になるならwin-winで最高です。
ユーザー詳細欄を読んでみると中には、「貧しい村に住んでます、ヤギとか牛のお世話の合間に趣味でつくってます」みたいなお母さんもいます。そういう人から「直接」買えるのも割と、いいですよね。もしお母さんが、例えば村から都市部の観光地まで持っていって実店舗で売る場合、あるいは遠くの国へ輸出する場合、取次業者が入る必要がある。そこでぼったくられたりしない(そんなことあるのか知らないけど)わけだから。「ユーザー詳細」のところを、動画付きで・自己紹介含んで書いてくれているお店もあるので、「生産者の顔」を見ながら買うのも楽しいかも。
私だって本当は海外旅行に行きたいんです!(突然の心の叫び)でも、海外が苦手、英語が苦手な夫と、小さな子たち二人を連れて遠くまで行くの、ものすごく気が重い…。自由に海外旅行できるようになるまで、まだしばらくかかりそうですし、それまではEtsyで世界を旅したい、と思ってます。

メキシコ オトミ刺繍

東南アジア モン族の刺繍
Etsyが好きな理由その4 日本だと高いものが安い(こともある)
そもそもEtsyは、送料を除けば、まあまあ「現地価格」に近い金額で売っている場所なので、「日本で買うと高いものがEtsyでは安い」ってことも当然あると思います。先に書いたように、取次業者ではなく生産者から直接買えるものもあるわけで。それを探すのが醍醐味だと思いますね。あと、海外の人はメッセージとか送っても嫌がらないです。値切り交渉したり、セットで売ってくださいと頼んだり、色々とコミュニケーション取るのも楽しいです。英語圏以外の人も多いので、お互いニュアンスで通じますw メッセージを送る機能もあるので、慣れてきたら翻訳ツールとか使って、会話してみたり値切ってみるのも良いかも。
さて、デメリットも当然ありますので、それらもキチンと書いてみましょう。
Etsyのデメリットその1 送料が高い&届くまで時間がかかる
送料って売り手がどう調整しているのか、私はよくわからないのですが、やっぱり国によっては「高っ!」という場所もあります。また、届くまでには時間がかかります。ファストシッピングなど使えば別ですが、通常ヨーロッパからだと二週間ぐらいは余裕でかかります。Amazonプライム翌日配送にどっぷり浸かった日本人には…この二週間はなかなかしんどいですね。「そんなに急いでない&日本や自分の住む街では手に入りにくい」買い物がおすすめです。忘れた頃にやってくるこの感じ、「あしながおじさんから突然贈り物が届いたごっこ」みたいな風に考えると楽しいぞ。
「送料無料」にしている商品やお店も一部ありますので、それで探すのも良いですね。エアメールってやっぱ届いた時に特別感ありますよ。切手とかカワイイし。
PayPal でしか払えないお店や、日本に配送してないと書いてるお店もありますが、メッセージで聞くと「大丈夫だよ」と言われたりもします。

商品ごとにこういうの書いてある
Etsyのデメリットその2 探しづらい
以前はかわいいと思うものをなかなか見つけにくい場だったのですが、最近はレコメンド機能が充実してきました。
商品、そしてショップをどんどんお気に入りにしましょう!そうすると、似た感じの商品やショップをどんどんおすすめしてくれます。私は、気がついたら商品を1000以上お気に入りしてました。どんな物欲だ。
あと、検索語を英語でいれる際に、工夫をしましょう。「北欧っぽい柄の手袋」はnordic mitten 、「刺繍のアクセサリー」はembroidery accesary です。otomi、Scandinavian、suzani、geometric、Halloween とか色々やってみてね。
返品もできるお店が多いです、やったことないけど。★によるレビューがあって、Etsiyだと基本的に4以上が当たり前ですが、たくさん売った実績がある&レビューが★4つ以上のところだと安心ですね。最近は配送追跡もできるっぽいです。

★がユーザー評価、その横の数字が購入実績数です
私が買ったモノとお店を紹介します
気が付くといろんなもの買ってました。あんまり高いものは買ってません。
https://etsy.me/2Q1TNEZ
Alphabetbags
ピンバッジです。ピンバッジもすごくいろんなデザインあって面白いです。
1個あたり7ユーロ、800円くらいです。

サコッシュにつけたりすると可愛いかなって
https://etsy.me/2Qhf77R
Vliving
クッションカバー
ここのお店どれも可愛くて、まだまだ買い物したいのですが、セールになっていたのでそれらを中心に買いました。本当はポンポンがついていたクッションカバーもあったのですが、ネコに取られました…。
セール含む10-18USD、1200~2000円くらい。

ポンポンは猫たちに喰いちぎられました…

ラッピングも可愛いですよ
https://etsy.me/2tRFeLx
Bubblesky
ピアス
ふたつ買いました。送料が13USD、ふたつで40ドルくらいだったので送料込み4500円くらいかな。

ピアスはよく買ってます
shaktiwali
ミャオ族の指輪
送料込み33ユーロ 4000円くらい
写真より実物の方がちょっと色がくすんでいました。そういうことはたまにあります。
でもすごく気に入っているため、また買いたいです。

仕様はちとボロいがどちゃくそ可愛いデザイン
https://etsy.me/2sjvz09
Dana jewellery
幾何学ピアス
ピアス送料込み2つで50ユーロ 一個3000円くらい
ここのは関税で一度開封された形跡がありましたが、それはお店にも不可抗力なのでは…と思いましたw

関税で一回開封された形跡がありましたw
https://etsy.me/2FRTQNn
totParis
ヘアバンド
25ユーロ 3000円くらい
日本でヘアバンド買おうとすると、だいたい暗い色の無地で、ちょっと変わったデザインだと5000円くらいするので…

ヘアバンド大好き!また買いたいけどいまショートヘアだ
https://etsy.me/37iKtCx
Jolanta knit
手袋
送料込み38ユーロ 4500円くらい
こういうの東京蚤の市で買うと7000円近くしますよ…。実物めっちゃ可愛いので大好きです。みんなも買ってみて。リトアニアはじめバルト三国って手芸に伝統あるよね。

この手袋がいちばん「買って良かった」かも
※おまけ ロシアから絵葉書を買ったことがあったのですが、とつぜんクリスマスカードが送られてきて嬉しかったです

ロシアってチェコに負けないkawaii文化あります
https://etsy.me/37hYbW8
Taste vintage
クリスマスの飾り(ビンテージ)
送料込み22ユーロ
クリスマスのオーナメントはビンテージが可愛いのでは、とここ数年思っていて、毎年ちょっとずつ買い足してます。

ラトビアめちゃくちゃ面白い国です
デジタルダウンロード
1デザインあたり100円~200円くらい
https://etsy.me/2F6IVzf
D&Ddegital delights
https://etsy.me/39nZ1m3
Past paper pretties
https://etsy.me/36oydje
Artgaze
ビンテージで著作権が切れているデザインを、ダウンロードで売っているお店があると気づきました。商用利用はお店によって可能なところとそうでないところがあるようですが、販売ではなく単にデザインをいじって、ネットプリント配布してみました。
まだまだかわいいデザインあるので、アレンジしてポストカードとか作ってみたい。
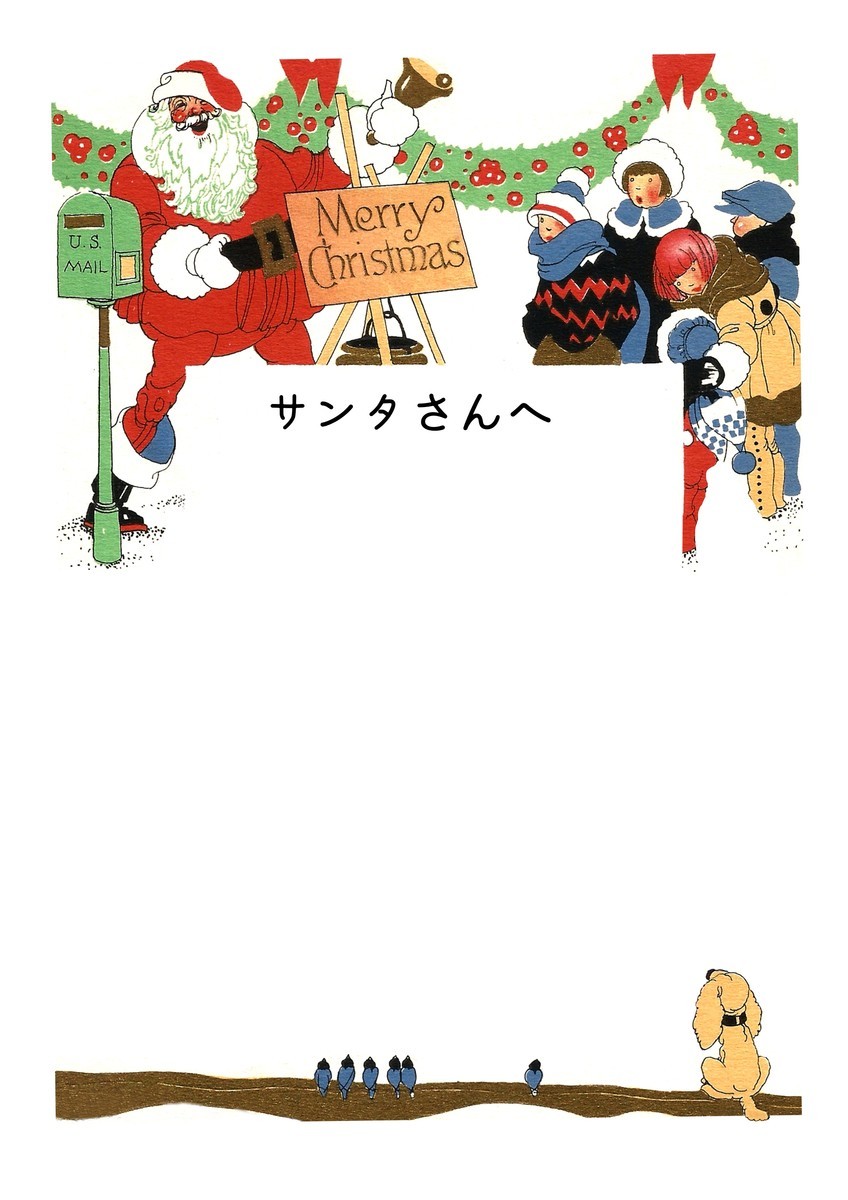
ネットプリントで頒布しました

字とかは私が足してます。左のはNY公共図書館のパブリックドメイン。
EarthlyGoodHome
布
送料込み89USD 9700円くらい
ソファーにかかってる、十字の柄のやつです。写真よりも生成り色だったので、あれ~と思ったのですが、使ってるうちに気に入ってきました。
猫がポンポンを喰っていますね。

ポンポンは喰いちぎられた…
https://etsy.me/2Qu5xzd
Slivkatlier
ピアス
送料無料、なぜかちょっと割引してくれて、15ユーロ。1800円くらい
これが一昨日ぐらいにスロバキアから届いた買い物です。「クリスマスに間に合わないけど大丈夫?」って連絡くれたり、とても優しいお店でした。届いたらショップカードにインスタのアカウントが書いてあって、見に行ったら、「これは私にとってもけっこう特別なやつで、日本に行くんだよ!」といったことが書いてあって、なんかすごく嬉しかったので私もインスタに載せてメンションしておきましたw

このピアスは彼女にとっても特別だったって。
他にもまだ買ったものあるのですが、ざっとこんなとこです。
最後のピアスみたいな体験ができると、海外からの買い物って楽しいなあ~と思ったりします。スロバキアってどんなとこなんだろ、いつか行ってみたいなあと思えたりするからですね。
せっかくインターネットが普及して、海外の人ともサッと繋がれるようになったのですし、「間に大資本(「有名ショップのお墨付き」とか含む)を挟まない買い物」がもっと進んでもいいんじゃないか?と思っていて、こういう記事を書いてます。直接購入できる方はそうやって楽しんでもらって、「やっぱり面倒」という人には、私が「店舗持たないバイヤー」としてちょっとずつ仕入れてお譲りする、みたいなのもやってみようかな?と思っています。
→というEtsy好きが高じて、webショップを開きました!
セラーと直接会話をして、商品をロットで仕入れて販売したり、しております。よければご覧ください。
2020cordelia.theshop.jp
インスタのフォローもお願いします
https://www.instagram.com/cordelia_kobeni/
大事なことを書くの忘れてました、Etsyは「アプリ」でお買い物が便利です!
PCからだと国別とか色別検索もできますが、基本はアプリがいいと思います。
ではでは。少しでもEtsyメイトが増えたら嬉しいなって思います。
皆さんも楽しいEtsyライフを!
過去のEtsy関連記事はこちらです。1~4まであります。
ETSY カテゴリーの記事一覧 - kobeniの日記